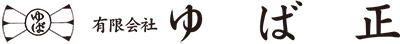こだわり
ゆば正のものづくりは、「食べる人が安心できること」を出発点にしています。
その日に食べる分だけを必要な分だけ製造し、保存のために添加物に頼るのではなく、鮮度と技術で味を保つのが私たちの姿勢です。
製造工程の多くは機械に任せることなく、昔ながらの手作業で進めています。湯葉の引き上げ加減も、生麩の練り加減も、胡麻豆腐の炊き上げ加減も、すべてが感覚と経験に支えられた仕事です。
一人ひとりが職人として、食材の状態を見極め、同じ品質を守り続ける。それが、ゆば正の変わらないこだわりです。
大豆

北海道産 大粒大豆を使用。
湯葉の味と質感を左右するのは、何よりも大豆の力です。
ゆば正では、長年にわたり北海道産の大粒大豆を使用しています。寒暖差の大きな気候で育つことで、甘みと旨みをしっかり蓄えた大豆は、豆乳にした際に雑味が少なく、風味豊かでクリアな味わいに仕上がります。
中でも、湯葉に適した品種・等級のものを選定し、粒の揃い・油分・タンパク質の質などを総合的に見て仕入れを行っています。年によっては産地や品種の切り替えも行いますが、品質を一定に保つために、試作と比較を欠かしません。
また、湯葉として引き上げたときの“膜の張り方”“裂けにくさ”といった仕上がりの安定感も、この大豆によって実現しています。味だけでなく、現場での扱いやすさにもつながる重要な素材です。
国産大豆
大豆を原料とする加工品は豆腐や湯葉だけでなく、味噌・醤油・納豆・きな粉等があります。
日本の食用大豆の消費量約350~390万トンに対しての国産大豆の生産量25万トン、自給率が約7%しかありませんので、多くをアメリカ等からの輸入に頼っています。
さらに言えば、ユネスコ無形文化遺産にも登録された「和食」、その中でも日本の伝統的食品である大豆加工品の多くが輸入原料で製造されている状況です。
和食文化が評価される点として、国内各地域の良い素材を使い、その良さを引き出すという技法が1つとして挙げられています。にもかかわらず、今、良い素材を使って丁寧にモノを作るということを当たり前にはできない世の中になっているように思います。
弊社は幸いなことに、モノの価値を正しく判断して下さる多くのお客様にお付き合い頂いております。
これからも良い素材を使って丁寧にモノを作ることを守り続け、微力ながら日本の文化を守ることに繋がればと願っています。
水

もうひとつ、私たちが大切にしているのが水です。
湯葉や生麩、胡麻豆腐は、全体の多くを水分が占める食べ物。だからこそ、仕込み水の質が、口当たりや風味の印象を大きく左右します。
ゆば正では、神戸市の上水道をさらに浄水ろ過し、不要な臭いや硬さを取り除いた水を使用しています。湯葉に使う豆乳の滑らかさを引き出し、生麩のコシを支え、胡麻豆腐では素材の香りを邪魔しない。そんな“支える水”であることが理想です。
目に見えにくい部分ではありますが、毎日口に入るものだからこそ、何気ない水のひとつにも手を抜きません。安心して使っていただける品質を支える、影の立役者です。
地産地消

ゆば正では、品質を第一に考えた素材選びを行う一方で、地域の農産物を活かす“地産地消”の取り組みにも力を入れています。
その一環として、兵庫県産の大豆を使用した湯葉の製造にも取り組んでいます。
兵庫県内の農家さんが育てた大豆は、やわらかな甘みと豊かな香りが特徴で、湯葉に仕上げるとふくよかな味わいが引き立ちます。
また、地元で収穫された新鮮な大豆を使うことで、輸送による劣化や時間差を減らし、より鮮度の高い状態で製造に取りかかれるのも大きな利点です。
「地元の食材を地元の料理に」という考えのもと、地域の料理店様とも連携しながら、兵庫ならではの味づくりに貢献できるよう努めています。
すべてのロットで兵庫県産大豆を使用しているわけではありませんが、ご希望に応じて対応可能ですので、地元食材にこだわりたい方はぜひお気軽にご相談ください。
湯葉の製造工程
当社で使用している大豆は、さきほど説明させて頂いた北海道産大粒大豆を主原料として製造しております。
STEP1

大豆を一晩水につけて戻します。
気温水温によって大豆の膨らみ方が違うので、氷やお湯をいれ年間通して同じ状態にします。
STEP2

大豆を水と一緒に石臼の機械で擂り潰します。これを“呉(ご)”といいます。
STEP3

呉を加熱します。当社ではボイラーによる圧力釜で一気に炊き上げます。
STEP4

加熱後、豆乳とおからに分けます。
このときに湯葉の木目を細かくするために、目の異なったメッシュで3回漉していきます。
そうして出来上がったものが豆乳になります。
STEP5

出来上がった豆乳を湯葉釜に入れて木枠で仕切り、沸騰しないように火加減をして、
数分後に豆乳の表面に膜がはってきます。これが“湯葉”となります。
湯葉は1回の釜から20回程度引上げていきます。
最初の方の湯葉は、品質も良く色も淡く木目が細かいものになります。
また、最初は乳白色だった豆乳が次第に薄黄色、褐色へと変化し、湯葉のしわもも大きい物になり、
湯葉の硬さ、風味、成分にも違いが出てきます。